「早生まれの子って、保育園で不利なのかな…」
おむつが外れていない、言葉がまだゆっくり、周りの子に比べてちょっと幼い──
そんな姿を見ると、「うちの子、大丈夫かな」と心配になることってありますよね。
実際に「早生まれは損」「発達が遅れやすい」といった声もよく聞かれるため、気になってしまうのは当然のこと。
でも本当に、“早生まれ”は保育園で不利なのでしょうか?
この記事では、そんな不安に対してデータや保育現場の声をもとに検証しながら、
親としてどんな関わり方や対策ができるのかを具体的に紹介していきます。
最後まで読んでいただければ、きっと「うちの子、このままで大丈夫」と思えるはずです。
そもそも「早生まれは損」と言われる理由とは?

「早生まれの子は保育園で不利かもしれない」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際、ネットやママ友との会話でも「発達が遅れがち」「ついていけない」といった声がちらほら聞こえてきます。
けれども、本当に“損”なのでしょうか?
そもそも、早生まれとはどの時期を指すのか、そしてなぜそのように言われるのか──まずはその背景から整理してみましょう。
早生まれとはいつ生まれた子ども?
「早生まれ」という言葉、なんとなく聞いたことがあるけれど、実際にはいつ生まれた子どもを指すのかご存じですか?
日本の学年区切りは4月1日。そのため、1月1日〜4月1日までに生まれた子どもは「早生まれ」と呼ばれます。
たとえば、2020年4月2日生まれの子と、2021年3月30日生まれの子は同じ学年になりますが、実際には約1年近い発達差があります。
この年齢差が、集団生活や保育園での発達・行動面において「不利になるのでは?」というイメージにつながることがあるのです。
なぜ「損」と言われるのか?よくあるイメージと声
保護者のあいだで「早生まれは損」と言われる背景には、いくつかの声や体験談があります。たとえば…
- 周りの子より身体が小さく見える
- おむつ外れや会話が遅れているように感じる
- 集団行動についていけていないと感じる
こういった一見目立つ差が、「やっぱり早生まれは不利なのかも…」という不安につながっているのです。
しかしこれは、あくまで“見た目の一時的な差”であることが多く、成長とともに解消されるケースがほとんどです。
このあと、実際のデータと保育現場の声を交えながら、「本当に不利なのか?」を深掘りしていきますね。
保育園で本当に不利になる?データと現場の声から検証

「早生まれは保育園で不利」と言われると、やっぱりちょっと気になってしまいますよね。
確かに年齢の違いによる差は存在しますが、それが“ずっと続くもの”なのか、“どのくらい大きな影響があるのか”は、正しく知っておくことが大切です。
ここでは、実際のデータや保育の現場から見える「リアルな早生まれ事情」をご紹介します。
実際の発達や適応に差はあるのか?
1歳児・2歳児のうちは、月齢による成長の違いがはっきり出やすい時期です。
たとえば、早生まれの子はまだ「はいはい」や「一語文」だったりする一方、同じ学年の遅生まれの子は「走ったり会話したり」ができることもあります。
こうした差は確かにありますが、それは早生まれの子が遅れているのではなく、他の子が早いだけとも言えます。
大切なのは「平均」と比べるのではなく、「その子なりのペース」を見守る視点です。
保育士さんの本音「早生まれの子はこう見える」
保育現場で子どもたちを見ている保育士さんたちも、もちろん月齢による差を理解しています。
多くの保育士さんが口を揃えて言うのは、
「確かに年齢が低い子は最初はのんびり。でも、1年たてばみんなちゃんと追いついてくるんです」
実際、最初の1〜2ヶ月はサポートが必要な場面もありますが、慣れてきたら月齢差よりも性格や個性が目立つようになることがほとんどだそうです。
また、保育園側も「早生まれの子は手がかかる」とネガティブに捉えているわけではなく、年齢や成長に応じた関わり方を心得ているプロ集団なので、安心して任せて大丈夫です。
統計から見る早生まれの傾向と現実
文部科学省の資料や発達心理学の研究などでも、**「早生まれの子どもは幼少期にやや遅れを感じることがあるが、就学後にはほとんど差がなくなる」**という傾向が明らかになっています。
一方で、親の意識が「心配だからこそ過干渉になる」「周りと比べて焦る」などに偏ると、それが子どもの自己肯定感に影響を与える可能性も指摘されています。
つまり、差があるかどうか以上に、“どう向き合うか”のほうが重要なのです。
早生まれでも安心!親ができる3つの具体的な対策

ここまで読んで、「確かに差はあるけれど、ちゃんとフォローできるんだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。
不安の正体が分かれば、あとは“どう備えるか”が大切です。
早生まれの子どもが安心して保育園生活を送れるよう、家庭でできること・保育園選びのポイント・心の持ち方の3つの視点からご紹介します!
① 家庭でできる声かけ・習慣の工夫
まずできるのが、**日々の関わりの中での「声かけ」や「習慣の工夫」**です。
- 小さな成功体験をたくさん作る(「自分でできたね!」とこまめに褒める)
- マイペースでもOKと伝える(「ゆっくりで大丈夫だよ」と肯定する)
- 親が焦らず待つ姿勢を見せる(比べない・比べさせない)
子どもは親の安心が何よりの安心です。「他の子より遅れてるかな…?」と感じても、まずは家庭の中で“できた!”を積み重ねていきましょう。
② 保育園選びでチェックすべきポイント
保育園によって、子どもの発達への理解やサポート体制には違いがあります。
早生まれのお子さんをもつご家庭におすすめなのは、以下のような視点で園を見てみることです。
- 年齢ではなく子ども一人ひとりに合わせた保育をしているか
- 月齢差を考慮して無理なく慣らし保育を進めてくれるか
- 「○○できない=ダメ」ではなく、温かく見守ってくれる雰囲気があるか
見学時には、実際の先生の声かけや、子どもたちの表情を観察してみるのもおすすめです。
③「比べない子育て」をするための考え方
保育園に通い始めると、自然と「周りの子と比べてしまう」ことが増えます。
でも、ここで大切にしたいのは「比べるのではなく、“その子の今”を見てあげること」。
とはいえ、頭では分かっていても、つい焦ってしまうのが親心。
だからこそ、自分自身にも優しく、「○○ちゃんには○○ちゃんのペースがある」と意識的に言葉にする習慣が大切です。
「この子の1年後は、今のあの子かもしれない」——そう思えると、心が少しラクになりますよ。
「情報に振り回されない」ために大切な視点

「早生まれは損」「発達が遅れる」など、気になる情報がネットや周囲からどんどん入ってくる時代。
子どものために一生懸命だからこそ、つい不安になってしまいますよね。
でも、そんなときこそ思い出してほしいのは、「情報よりも、目の前のわが子」。
最後に、“情報過多”な今の時代に、親として大切にしたい視点をお届けします。
育児の“正解”は一つじゃない
SNSや育児ブログ、ママ友の声…どれも大切な参考情報ではありますが、
「その子にとっての正解」が必ずしも「うちの子の正解」とは限りません。
早生まれの子でも、集団生活が得意な子、マイペースな子、本当にいろんなタイプがいます。
だからこそ、周りの情報に振り回されすぎず、「うちの子に合った関わり方」を大切にしてほしいのです。
子どもに合った環境と親の安心がいちばん大事
子どもにとって何より大切なのは、安心できる居場所と、安心して見守ってくれる大人の存在です。
どんなに良い保育園でも、親が不安なままだと、それが子どもにも伝わってしまうことがあります。
「この子はこの子のペースで大丈夫」「多少ゆっくりでも、その子らしく育ってくれたらOK」
そんなふうに構えていられたら、子どもにとっては何よりの安心材料になるのです。
まとめー早生まれでも大丈夫。大切なのは“安心できる環境”づくり
「早生まれは損かもしれない」「保育園で不利になるかも」
そんな声に不安を感じるのは、ごく自然なことです。
でも、この記事で見てきたように、
- 年齢差は確かにあるけれど、一時的なものであることが多い
- 保育士さんたちはその差を理解し、丁寧に対応してくれる
- 親の関わり方や園の選び方で、十分にフォローできる
という現実があります。
🌱 情報よりも、目の前のわが子を信じて。
小さな一歩が、ちゃんと未来につながっていきますよ。


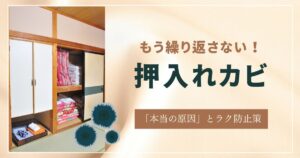







コメント